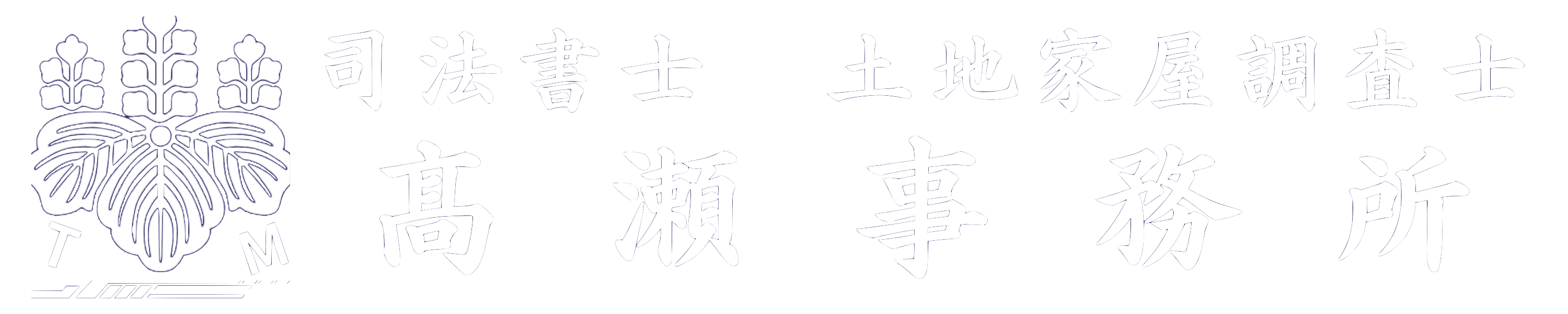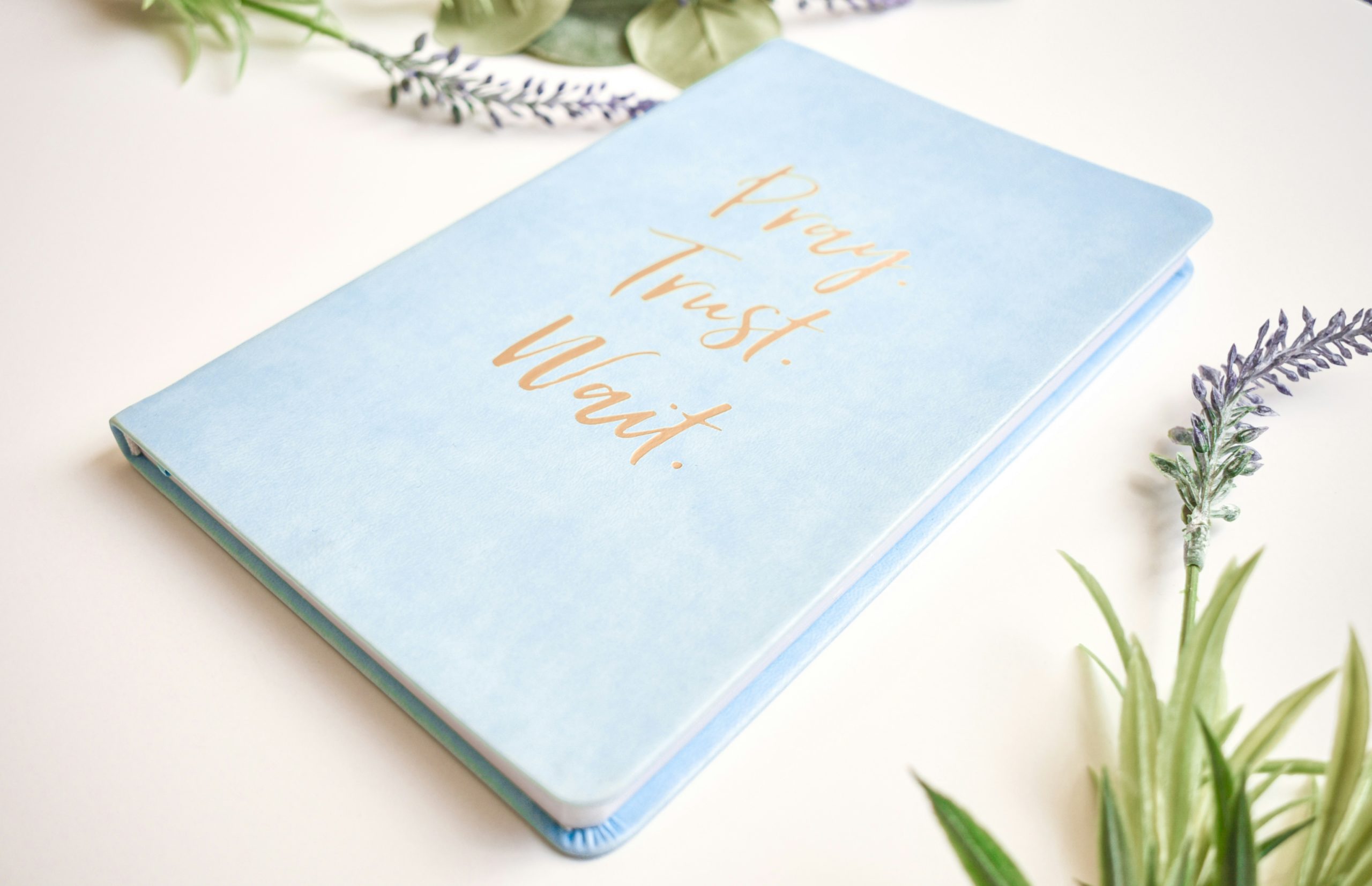
生前対策
髙瀬事務所の主な生前対策支援業務
司法書士・土地家屋調査士髙瀬事務所では、主に次のような生前対策に関する支援を行っております。
遺言書作成支援
- 子や親族に、相続手続きに時間や費用をかけさせてしまうのは申し訳ない
- 遺産相続で親族同士で揉めてほしくない
- 単身で、遺産がどうのようになってしまうのか心配
任意後見契約支援
- 単身であるため、自分の判断能力が衰えたときに、どうなってしまうのか不安。
- 将来、法定後見によるのではなく、信頼できる人に自信の財産管理、身上保護をお願いしたい。
民事信託契約支援
- 元気なうちに不動産など特定の財産について親族に管理、処分をまかせておきたい。
- 事業の後継者への承継を進めたいが、一抹の不安がある。
遺言書作成支援
「たいして相続させる財産がないから必要ない」と言われることがあります。しかし、 正しく遺言書を作成しておくことで、難しく専門的知識を必要とする相続手続をスムーズに進めることができ、親族間のトラブルに限らず、相続手続でのトラブルを避けることができるということを知っていただきたいと思います。 多額の財産が無いと思っておられたとしても、『遺言書を作成しておくべき主な事例』に思い当たる方は、是非とも遺言書の作成をご検討してください。
遺言書を作成しておくべき主な事例
- 相続人が多数いる、再婚前の子がいる
- 子がいない、相続人がいない
- 所有不動産、銀行口座が複数ある
- 会社を経営している
- 相続人の中に行方不明者や、意思表示に問題がある者がいる
- 相続人が相続手続ができるか不安がある
遺言書作成のメリット
メリット
- 生前のうちに遺産の分け方を決められる
- 遺産分割協議での相続争いや、協議不能を回避できる
- 遺贈することで相続人以外にも財産を渡すことができる
- 遺言書作成を検討することで、相続税対策を考える機会ができる
遺言書の種類と特徴
遺言書は法律の形式に沿って作成しなければならず、遺言によって効力を発生をさせることができる事項についても決まりがあります。
公正証書遺言
- 公証人が遺言者の意向に沿って法律で定めれれた要件を満たした遺言書を作成してくれるので、遺言内容及び形式について無効とされることがない
- 原本は公証役場で保管されるので紛失のリスクがない
- 家庭裁判所での検認が不要
- 公証人手数料が費用
法務局保管自筆証書遺言
- 形式チェックがなされるので、形式無効とされることはない
- 法務局で保管されるので、紛失のリスクがない
- 家庭裁判所での検認が不要
- 公正証書遺言よりも安価で利用が可能
- 遺言書情報証明書を請求するために一定の手続が必要
自筆証書遺言
- 誰にも内容を知られずに、すぐにでも作成可能
- 作成するのに特別な費用がかからない
- 遺言内容及び形式について無効となるリスクがある
- 紛失、改竄、発見されないリスクがある
- 家庭裁判所での検認が必要
おすすめは公正証書遺言
公正証書遺言を作成しておくことで、スムーズに遺産承継手続きを進めることができます。
他の方法では、遺言書情報証明書の請求や、家庭裁判所の検認手続きを経ないといけないのに対し、公正証書遺言では、比較的速やかに遺言執行にとりかかることが可能です。
また、公正証書遺言では、公証人が作成することになるので、遺言内容、遺言形式ともに無効となる心配はありません。
身近な親族に対する想いを遺し、相続手続きの負担を少なくことができる公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。

任意後見契約支援
任意後見契約とは、認知症等により判断能力が減退してしまった場合に備えて、あらかじめ信頼できる人に、財産管理や、身上保護について委任しておく契約です。
これに対して、任意後見制度を利用していない方の判断能力が減退してしまった場合の制度として、成年後見(法定後見)制度があります。
任意後見と成年後見
まず、任意後見と、成年後見の主な違いについて簡単にご紹介します。
任意後見
- 元気なうちに、信頼できる人(任意後見人)に対し、財産管理、身上保護をお願いすることができる。
- 公正証書により契約をしなければならない。
- 契約の効力が発生するのは、実際に判断能力が減退し、家庭裁判所による任意後見監督人(通常は専門職)の選任がなされた後。
- 任意後見人は、契約で定められた事項についてのみ、代理権を有する。
- 後見方針について、財産管理や、身上保護についての本人の希望をあらかじめ示すことができる。
成年後見
- 判断能力が減退した後に、家庭裁判所の審判によって、財産管理、身上保護をする人(成年後見人)が選任される。
- 後見開始の審判により、後見が開始する。
- 親族後見人が選任された場合、通常、後見支援信託の利用か、専門職後見監督人が選任される。
- 後見人は法定代理人として、包括的な代理権を有する。
- 成年後見人は、一般的な社会規範に基づき、財産管理や、身上保護を行う。
任意後見のメリット・デメリット
メリット
- 任意後見契約の締結時にライフプラン、指示書等を活用することにより、本人の希望に沿った後見を実現することができる。
- 信頼できる人に委任することができる。
- 任意後見契約は、法定後見に優先する。
- 任意後見を検討することで、将来の財産承継や、相続税対策などの終活を考える機会ができる
- 自己決定権の表れとして、原則、本人の同意がなければ任意後見契約が始まることはない。
デメリット
- 公正証書の作成費用がかかる。
- 任意後見監督人選任申立費用や、任意後見監督人の報酬が必要となる
- 任意後見監督人への定期事務報告が必要となる。
- 任意後見契約で定められた代理権以外の事項ついてはに対応できない
任意後見契約をおすすめします
任意後見のデメリットでご紹介した、任意後見監督人選任申立費用や、報酬、定期事務報告等については、法定後見でも同様ですので、特別なデメリットではありません。
代理権について、しっかりと検討して作成しておくことができれば、本当の意味でのデメリットは、公正証書作成費用がかかってしまうということになります。
しかしながら、法定後見が開始し、専門職の成年後見人が選任されてしてしまえば、本人が希望していたことが分からないため、一般的な社会規範に則って後見事務を行うことしかできなくなってしまい、そのことが制度批判のひとつになっていると考えられます。
信頼できる人に後見事務をお願いすることができ、ライフプラン、指示書等を活用することで、本人の希望する後見の実現のためにも、任意後見契約をおすすめします。
任意後見と一緒にご検討いただくこと
任意後見をご利用になられる際には、一緒に次の契約締結もご検討ください。
見守り契約・財産管理契約
任意後見契約は、本人の判断能力が減退し、任意後見監督人が選任された後に契約の効力が発生します。
そこで、契約の効力が発生するまでの間、どのタイミングで任意後見監督人選任申立をするのか、また、それまでの間に受任者にお願いしておきたいことなどを定めておくことで、スムーズに任意後見に移行できます。
死後事務委任契約
任意後見契約は、本人の死亡により終了します。
よって、任意後見人の代理権は失われてしますことになり、死後の事務処理についての代理権はありません。
そこで、葬儀や、埋葬、供養等に関する事を任意後見人にお願いしておきたい場合は、その旨の死後事務委任契約を締結しておくことをおすすめします。
民事信託契約支援
民事信託とは、信託法という法律に規定されているルールに従って、主に親族間等でなされる財産管理に関する契約のことです。 財産を持つ人(委託者)が、信頼できる人(受託者)に対し、契約によって定めた目的の範囲内で、特定の財産管理や処分等を任せる契約を信託契約といいます。そして信託契約では、信託された財産によって利益を受ける人(受益者)のために、受託者は、自己の名において契約に定められた目的に従って財産の管理、処分等を行います。
民事信託の利用シーン
民事信託は、主に次のような場面で利用されるようになってきています。
民事信託の具体例
認知症対策としての、民事信託の利用例をご紹介します。

父Aは、将来介護施設へ入所することになった場合、父A所有の自宅土地建物を売却し、介護施設への入所資金へ充てようと考えて、民事信託契約を利用することにし、信託契約は次の通りの内容とした。
信託契約の内容
【当事者】
委託者兼受益者 父 A
受託者 長男 B
【目的】
Aの生涯にわたる安定した生活の支援と最善の福祉を確保すること
【信託財産】
Aの自宅土地建物
不動産管理費用としての一定の資金
【信託財産の管理処分】
Bは、Aが介護施設へ入所することとなり、自宅土地建物が必要となくなったと判断するときは、自宅土地建物を売却し、その売却代金を介護施設の入所費用、施設利用料等に充てることができる。
父Aが認知症等により判断能力が減退してしまったとして、民事信託契約を締結していた場合と、そうでない場合、どのような違いがでるのかご紹介します。
民事信託を利用
していた場合
- 民事信託契約時に登記名義は長男Bへ変更していたため、受託者Bが買主と売買契約を締結
- Bが売主として売買代金を受領し、代金を信託財産とした。
民事信託を利用
していなかった場合
- 不動産の売却のため、家庭裁判所へ父Aの成年後見人選任申立をした。
- 不動産は自宅であるため、選任された成年後見人により家庭裁判所へ居住用不動産の売却許可申立が必要となった。
- 成年後見人と買主により売買契約を締結
- 売却代金は、成年後見人が管理用口座にて管理
民事信託を利用していなかった場合、父Aに成年後見人の選任が必要となるため、機動的な売却処分はできず、成年後見開始の審判及び居住用不動産の売却許可が必要となり、数ヶ月の時間的ロスが出てしまいます。これでは、売却機会を逃してしまうことも考えられます。
成年後見制度は、本人の権利保護のための制度であるため、時間がかかってしまうことは仕方のないところではありますが、家族、親族間で信頼関係が構築できているのであれば、民事信託契約を利用することも検討に値すると思います。
民事信託契約の注意点
民事信託は、自由な設計により成年後見制度では実現できない、積極的な資産の管理運用処分が可能です。しかしながら、契約の設計を誤れば、公的な監視、監督機能がないため、受託者の権限濫用のリスクにさらされたり、思わぬ課税負担が発生したりします。
そこで、民事信託を利用する際の主な注意点をご確認ください
民事信託の主な注意点
- 契約締結時に公正証書作成費用、登記費用などの初期費用がかかる
- 資産は受託者名義になるが、受託者固有の財産とは分別管理しなければならない
- 信託用金融機関口座の開設に対応していないところが多い
- 課税上、不明確な部分が未だ多く、設計によっては思わぬ課税負担が生じることがある
- 受託者の権限濫用を監視する仕組みを作ることは可能だが、公的監視の機能がない
- 信用のおける受託者の成り手が少ない(信託業法による規制)
- 契約による財産管理の仕組みであり、受託者に身上保護に関する権限はない
民事信託契約の検討をおすすめします
民事信託には、さまざまな注意点がございますが、しっかり検討し、上手く活用することができれば、後見制度では実現することのできない資産の積極的な運用が可能となります。また、それ以外でも、柔軟な設計をすることにより、遺言の代用としたり、スムーズな事業の承継に活用できたりもします。
将来のことについて不安があったり、子供たちに任せようと考えておられる場合、民事信託を利用することで、より早い段階で、次世代へ財産の管理運用をまかせながら、一定の監視、監督を行う設計が可能となる民事信託の利用をご検討されることをおすすめします。